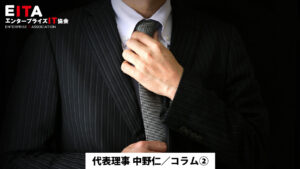まとめ
- 生成AIの進化により、ホワイトカラー業務の生産性と価値創出の方法が変わりつつあります
- 従来の「情報の非対称性」に頼った仕事のスタイルが見直され、組織内の力関係や人材評価の在り方も変化しています
- この変化に対応するには、継続的な学習習慣の獲得と、AIを前提とした業務設計への移行が重要になっています
1. 次々と訪れるAI技術の進化
2025年に入り、生成AIの進化スピードが加速しています。新たなAIによるインパクトある機能が次々と登場し、ビジネスの前提が変わりつつあります。例えば、GPTは画像生成で「ジブリ風」の絵を描き出せるようになったりしましたね。クリエイティブ領域にインパクトがある内容でしょう。
個人も企業がこれらの変化への対応を模索している状況です。早すぎる…。
この状況は技術の進化にとどまらず、ホワイトカラーの仕事の在り方にも影響を与えています。ナレッジワーカーやホワイトカラー系の職種では特に変化が顕著です。例えば、既に編集者やライターの仕事が変化し、従来の外注の仕方や価格設定が見直されてきています。
専門性の高かった業務がAIによって実行可能になるスピードが予想以上に速く、この「コモディティ化」の波に企業は対応を迫られています。技術の進歩が私たちの働き方を変えつつある気がします。
2. 学習習慣とキャリア発展の関係
この変化に対応するための重要な要素は、仕事の中で継続的に学習する習慣です。某ビックテックのような企業では、エンジニアだけでなく営業やコーポレート部門の社員も、週の20〜25%程度を学習に充てる文化があるようです。
一方、多くの日本企業では必要なときに情報を取りに行くという受動的なアプローチが見られます。「仕事の為に学習する」という概念が仕事の中に十分に組み込まれていないケースも少なくありません。この差はAI時代において影響を持つ可能性があります。
過去の経験や知識に頼る従来型の働き方では、タスクベースの発想になりがちです。「タスクが終われば評価される」という考え方に焦点が当たりますが、その価値は下がるかもしれません。20年前と今ではデジタルによりこなせるタスクの量は増えました。でも、報酬は同じ様に増えてません。生産性が上がるとということはタスクに対する価格の価値は下がるということでもあります。
一方で、学習を日常的に取り入れ、目的や理由を考える習慣がある人材は、変化に対応しやすいかもしれません。いままでルーティンのタスクで忙殺されていた部分を新たな分野への試行錯誤に使えるかもしれません。また、少ない人数で大きな仕事ができる可能性があります。そうなると、利益の配分比率は上げやすくなるかもしれません。
しかし、こうした学習習慣は若いうちに形成されることが多く、年齢を重ねると必要だから仕方なく最小限を学ぶという受動的なアプローチが定着しやすい傾向があります。新しい事を学ぶには気力と体力が必要ですからね。一度、身について手癖になった仕事を歳を取ってから変えることは相当難しいのではないでしょうか?
変化・学習する習慣がある人はまだ有利であり、そうではない人は厳しくなるかもしれません。
3. 生成AI前提の業務設計の影響
多くの企業で見られるのは、生成AIを活用できる人とそうでない人の間の生産性の違いです。会議の準備資料などでは、生成AIを活用して効率的に資料を作成できる人と従来のやり方で作成する人の間で、進め方の違いが生じることがあります。
これはコロナ禍初期にオンライン会議ツールの使用に慣れていない人がいる場合に見られた状況に類似しています。生成AIの場合は単なるツールの使い方だけでなく、業務の進め方や思考方法の変化も関係しています。
生成AIの特徴として、必要な知識や情報を提供するだけでなく、ドキュメント作成もサポートする点があります。これにより、従来は「特定の人だけが持つ情報」によって価値を提供していた経験者の役割が変わりつつあります。
情報の非対称性によって地位を維持していた層の優位性が減少し、AIを活用して効率的に業務を進める人材が注目されるようになっています。「教えてもらえなければAIに聞く」という選択肢の登場により、組織内の関係性も変化しています。
4. 経験による「情報の非対称性」の変化
従来の企業環境では、年次や経験によって情報格差があり、それが一種の構造を形成していました。若手に対するベテランの優位性として機能していた「知識と経験による情報の非対称性」が、生成AIによって薄れつつあるのではないでしょうか?
この変化のペースは予想よりも速く、当初は5年程度かかると考えられていたのですが、もう少し早くなる予感がしています。
特にデジタル領域の経験や知識は獲得も比較的早いが、陳腐化も早いという特徴があります。農業のような物理的な仕事は、季節性があるため経験の蓄積に時間がかかり、急速に変化することは少ないでしょう。
一方、ホワイトカラーの仕事は「情報の追加・修正・蓄積・調整」が主な業務であり、パソコン作業の多くがこうした内容です。これらはAIが得意とする領域と重なる部分が多いです。
「速いスピードで移動しているが、同じ場所を何周もしている」ような感覚は、特にデジタル分野のキャリアを持つ人々にとって身近な課題かもしれません。やっていることは実はそれほど変わっていない。ただ、スピードだけが上がっている。車輪の回転速度だけが上がるラットレースみたいなものでしょうか。
シニアは後何年戦えるのかを体力・気力から考えて、自分の労働者としての賞味期限切れと向かい合う必要があるかもしれません。

5. 組織とリーダーシップの適応
生成AIがもたらす変化は技術面だけでなく、組織構造やリーダーシップのあり方にも及んでいます。トップダウン型のマネジメントスタイルでは、上層部が意思決定を集中させ、中間管理職は指示を伝える役割になりがちです。
このような環境では、生成AIのような新しい技術を組織全体に浸透させることが難しい場合があります。強い統制がある組織では、中間層が判断する機会や自走する機会が限られ、マネジメント力を発揮しにくいことがあります。
トップとメンバーが直接つながる組織構造では、情報伝達の効率化で中間を抜き指示を明確に実行できる状態にする。情報収集と集約という中間管理職が行っていた機能を生成AIが効率化してゆく。マネージャーはより実行に集中でき、そのリーダーシップをもって評価される比重が上がるかもしれません。
6. 評価・育成システムの新しい形
生成AIの発展は、人事評価や育成の方法にも変化をもたらす可能性があります。従来の評価システムでは、マネージャーの主観や上司との関係性が影響することがありましたが、AIを活用することでより客観的な評価基準を導入する方向性も考えられます。下記の様な形に変わるかもしれません。
- . 普段から評価基準になる様な定性・定量情報を情報をシステムに蓄積しておき、評価基準を設定する。
- AIが評価のベースを作成したたき台作る。マネージャーがそれを調整する
これによって評価の客観性が高まるだけでなく、人物評価から行動・業績評価へのシフトが進む可能性もあります。人間関係の要素が混在する従来の評価から、より透明性のある評価へと変わっていくことで、組織内のコミュニケーションも変化していくでしょう。
より客観的な基準での評価が広がることで、パフォーマンスに基づいた評価文化が形成されていく可能性があります。というと、いいことの様に思えますが、透明化が進みより言い訳ができない状態になるということです。労働者としては常に全力で走り、評価されるという状態とも言えなくもないです。
7. これからのキャリア戦略:変化への適応と継続学習
この変化の時期に適応していくためには、どのようなキャリア戦略が考えられるでしょうか。重要な要素の一つは、変化を受け入れ、学び続ける姿勢です。自分の経験が異なる形で評価される可能性を認識し、新しい技術やツールを学び続けることが役立つでしょう。というより、学びと変化を前提としないと、人の形をした産業廃棄物・組織負債として扱われるかもしれません。
また、自分自身の強みと弱みを分析し、「どこで価値を提供するか」を意識的に選ぶことも一つのアプローチです。自分に合った場所を見つける過程で、副業などで関わりながら徐々に深く関与していくという柔軟な働き方も選択肢の一つです。どこで戦うべきか、誰と一緒に組むべきかは試行錯誤の先にしか見つからないと思います。
組織に依存するのではなく、「自分のキャリアを主体的に考える」視点を持ち、バランスを取りながら、自分でキャリアを形作っていく姿勢が役立つかもしれません。このキャリアのバランスを取ることが、変化の時代を生きる上での重要なテーマとなりそうです。主体性が試される側面が強くはなりそうです。
結論
- 生成AIの進化により身につけた経験や知識の陳腐化は早くなる予感がします
- この変化に対応するには、継続的な学習習慣を身につけ、AIを前提とした仕事の仕方を模索する必要がありそうです
- 組織としてもリーダーシップや評価制度の見直しを含め、必要な人と必要ではない人を決めていく局面がくるかもしれません
筆者
中野 仁(Jin Nakano)
エンタープライズIT協会代表理事/AnityA 代表取締役