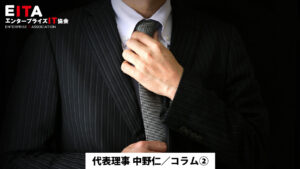まとめ
- 独立という選択肢は、会社員の給与体系とは異なる次元の経済合理性を持つため、経験者にとって事業会社への復帰は単純な条件比較では判断しにくい。
- ITリーダー、特にCIOのポジションは、経営が負うべき責任を押し付けられる一方で、実行に必要な権限が与えられず「割に合わない」構造に陥りやすい。
- 真に組織を動かすには、一人のリーダーだけでなく、専門性を持つ自律したチームが必要不可欠であり、個人の能力だけに依存する体制には限界がある。
1. 年収1000万円超えでも心が動かない、シンプルな理由
同じ様に独立した人同士での会話で、転職のスカウトで「年収1000万円以上の部長級」「CIO候補」という、一見すると悪くないお話をいただくことがあります。しかし、独立して自分の会社を経営している立場からすると、この条件に経済的な魅力を感じることは、残念ながら余り持てなくなったという話題がでます。
これは単に金額の大小だけの話ではありません。そこには、会社員と独立した事業主との間にある、見過ごされがちな「経済合理性」の大きな壁が存在します。
独立して自ら事業を動かすという道を選ぶと、会社員時代には想定し得なかったほどの事業規模や収益の可能性が拓けることがあります。会社から与えられる給与とは質的に異なり、事業の成長が直接自らの成果として反映される世界です。一度その経験をすると、以前の評価基準だけでは物事を判断しにくくなります。
さらに重要なのが、報酬の考え方です。
給与所得は、収入が上がるほど税率も上がる累進課税が適用されます。年収が2倍になっても、手取りが2倍になるわけではありません。一方で、会社を経営していれば、事業に必要な支出を経費として計上でき、自分で役員報酬を決められます。自分で自分の報酬を決め、税負担をある程度はコントロールすることが可能です。これは、資金繰り・資産形成において非常に大きな違いを生みます。
会社員という立場では、この様な事はできません。源泉徴収と累進課税というシステムにより、事業者で例えるならば「売上(給与総額)に直接課税されている」ような状態とも言えます。そうした経験の後で、再び給与所得という一つの評価軸の世界に戻ることに、どれほどの意味を見出せるだろうか、という問いが生まれるのです。
2. なぜITリーダーのポジションは「割に合わない」と感じられるのか
経済的な側面だけでなく、仕事の内容に目を向けても、事業会社のITリーダー、特にCIO(最高情報責任者)やそれに準ずるポジションには、根深い「構造的に割に合わない」問題が潜んでいると感じます。
会社員時代、こんな経験はありませんでしたか?
- 経営層から「AIを使って何かいい感じにしておいて」といった、曖昧で丸投げのような指示が飛んでくる。
- コストカットや業務効率化を進めると、現場の各部門から「今まで使えたツールが使えなくなった」「なぜうちの部門だけ厳しくするんだ」と恨みを買ってしまう。
- セキュリティを強化すれば、便利さが損なわれるため、やはり反発が起きる。
こうした状況でITリーダーは、経営と現場の「板挟み」になります。一生懸命に全社のための仕事をすればするほど、社内の誰かから恨まれたり、反感を買ったりしてしまうのです。
本来、ガバナンスやセキュリティといった全社に関わる方針の最終的な意思決定と責任は、経営陣、すなわち取締役会が負うべきものです。しかし、多くの企業では、その実行の矢面に立たされ、結果責任まで問われるのがIT部門の責任者です。
これは、極めて困難な役割です。そして、この苦労に見合うだけの報酬や権限が与えられているかというと、残念ながら、そうではないケースが多いように見受けられます。1000万円超えのマネージャー職という待遇でどこまで対価として認められるかは人それぞれですが、本気でやればやるほど割に合わなさを感じてしまうようです。
3. 「CIO候補」という役職に潜む、見えざる罠
ITリーダーを募集する際に、「CIO候補」という肩書きが使われることがあります。しかし、この「候補」という言葉には、注意が必要かもしれません。
基幹システムの刷新や各所に影響がある水準のセキュリティ施策といった全社規模のプロジェクトは、各部門の協力なしには成し遂げられません。そこには必ず利害の対立や、変化への抵抗が生まれます。
こうした障壁を乗り越えて物事を前に進めるためには、「これは会社として決定した方針です」と断行できるだけの強い権限が不可欠です。理想を言えば、それは取締役級の権限でようやく五分五分、オーナー社長でやや可能性ありみたいな状態も珍しくありません。
「CIO候補」というポジションでは、この最も重要な権限が与えられていない可能性があります。十分な権限がないまま、結果だけを求められる。これは、非常に厳しい状況と言わざるを得ません。
もし前任者がいるポジションであれば、「なぜその人は辞めてしまったのか?」を深く考える必要があります。『鋼の錬金術師』に「勘のいいガキは嫌いだよ」という有名なセリフがありますが、まさにそれで、賢明な人ほど、そのポジションが抱える構造的な問題に気づき、長くは留まらないのかもしれません。
4. 高いハードルに耐えうる人材は、どこにいるのか?
では、こうした難易度の高い役割をこなせる人材はどこにいるのでしょうか。
私の周りを見ていると、事業会社でCIOやそれに準ずるレベルで活躍できるような実力を持った人たちは、多くの場合、次のどちらかの道を選んでいるように思います。
- 独立して、自分のコンサルティングファーム・開発会社を立ち上げる
- より高い報酬を求めて、外資系の企業やコンサルティングファームに移る
彼らは、自分のスキルが労働市場でどれだけの価値を持つかを理解しています。そして、その価値を最も正当に評価してくれる場所を選ぶのです。
すると、事業会社が採用市場で出会えるのは、また別のタイプの人材になってきます。例えば、
- 家庭の事情などで安定を重視し、リスクを取ることを避ける方
- まだ経験は浅いが、ポテンシャルを期待されて次のステップを目指す方
- キャリアアップのために職場を転々とされている方
もちろん、こうした方々が優秀でないという意味では全くありません。しかし、企業が漠然と「スーパーマンのようなITリーダー」を求めているのであれば、そこには大きなギャップが存在している可能性があります。企業が求める人材と、市場にいる人材との間に、認識のズレが生じているのです。
5. リーダー一人では戦えない。機能するチームに必要なこと
ここまで、ITリーダーというポジションの難しさについてお話ししてきました。しかし、これは決して個人の能力だけの問題ではありません。最大の問題は、「たった一人のリーダーを外部から採用すれば、すべてが解決する」という発想そのものにあるのかもしれません。
どれだけ優秀な司令官でも、一人では戦争に勝てません。その戦略を実行する優秀な部隊が必要です。
IT組織も同じです。CIOというリーダーがいたとしても、その下で実際にプロジェクトを推進する部長級や課長級の、自律して動ける「実行役」がいなければ、組織は機能しません。
企業のシステムはデータが扱うほぼ全ての領域に達します。一人格で適切な判断を下せる処理容量を超えます。
理想的なIT組織は、単なるピラミッドではなく、専門性を持ったチームの集合体です。例えば、
- ビジネス:ビジネスの成長に直接貢献するIT活用を考えるチーム
- コーポレート:セキュリティやガバナンスといった守りを固めるチーム
- インフラ:全社的なITインフラを支えるチーム
これらはそれぞれ専門性が異なり、時には利害が対立することもあります。CIOの役割とは、こうした多様なチームをまとめ上げ、一つの大きな方針の下で機能させる、いわば「オーケストラの指揮者」のようなものです。
もし、あなたの会社が外部からITリーダーを探しているのなら、一度立ち止まって考えてみてください。「なぜ、内部から後継者が育たなかったのだろうか?」と。その問いの答えにこそ、本当に取り組むべき組織課題が隠れているのかもしれません。
結論
事業会社で優秀なITリーダーが定着しにくいのは、個人の資質の問題ではなく、経済合理性、責任と権限の不均衡といった構造的な課題に起因することが多いです。
この問題を解決するには、一人のスーパーマンに依存するのではなく、リーダーが正しく機能できる権限と、それを支える専門的なチームを組織として構築する視点が不可欠です。
企業は採用活動と並行して、自社のIT組織が抱える構造的な課題そのものに目を向ける必要があるのかもしれません。
筆者
中野 仁(Jin Nakano)
エンタープライズIT協会代表理事/AnityA 代表取締役