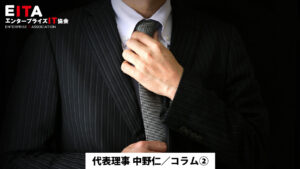まとめ
- 私たちが参加している資本主義というゲームは、必ずしも労働者に有利なルールで設計されているわけではありません。
- お金とは、労働市場に提供している自分の時間や選択する権利を買い戻すための手段になり得ます。
- 加速する環境の中では、自分がどのようなルールのゲームに参加しているかを自覚し、能動的に行動を考えることが重要です。
1. はじめに:なぜ、若者にこの話をするのか
街で新入社員らしきフレッシュな若者たちを見かける季節になりました。彼ら彼女らを見ると、ついお節介な気持ちが湧き上がり、20代の方に会うたびに、これからお話しするような内容を伝えるようにしています。
もちろん、多くの場合、相手は「( ゚д゚)ポカーン」とした顔をします。無理もありません。私自身も若い頃は、きっと同じような反応をしたでしょう。それでも、これは私が若い頃にこそ聞いておきたかった、とても大切なことだと考えているので、少し面倒だと思われても、伝え続けています。
この話は、誰かを批判したり、特定の生き方を押し付けたりするものではありません。ましてや「労働者は被害者で、資本家・経営者が加害者だ」といった単純な善悪の話でもありません。これは、かつて何者でもなく、大切なものも分からずに途方に暮れていた若者だった頃の自分自身に語りかけるような、時空を超えた独り言なのかもしれません。
これから語るのは、私が見てきた世界の報告です。もし、あなたが自分のいる場所や、これからの歩き方について少しでも考えるきっかけになれば、それ以上に嬉しいことはありません。
2. 私たちが参加している「ゲームのルール」を知る
まず、私たちが生きる資本主義というゲームが、どのようなルールで動いていのかを考えてみることから始めましょう。このゲームは、残念ながら、労働者、つまり「持たざる者」にとって、必ずしも有利なルールにはなっていない可能性があります。むしろ、資本家や経営者といった「持つ者」に有利に働くようにできています。
この構造の中で、労働者は「生かさず殺さず」の労働力として扱われやすい側面があります。もちろん、職業選択の自由はありますが、生活のために働くという状況下では、その選択権は実質的に制限されていると言えるかもしれません。
一方で、現在の日本は社会基盤が非常に安定しています。普通に生活していれば、最低限の暮らしが保障され、食べるために犯罪に手を染めるほど追い詰められることはほとんどありません。これは本当に凄いことであり、「最も成功した社会主義」と評されるのも頷けます。
しかし、この「安全」と「安定」が、逆に行動を妨げる要因になることもあります。危機感や緊張感が生まれにくいため、現状維持を望む気持ちが強くなります。その結果、新しいことを学んだり、リスクを取って行動したりする動機が生まれにくくなるのです。
生物として「安全・安定」を求めるのは本能ですが、その心地よさに浸り続けるうちに、気づかないうちに資本を蓄える機会を失い、「持たざる者」の立場に固定されてしまう可能性があるのです。

3. 「お金」で自分の人生を買い戻すという考え方
では、このゲームの中で、私たちはどうすれば良いのでしょうか。その鍵の一つが「お金」に対する考え方です。
私にとって、お金を持つということは、自らの人生の選択肢を買い戻す事だと思います。つまり、人生の時間、そして人としての資格を労働市場から買い戻す行為だと考えています。会社に雇用されるということは、報酬とある程度の安定と引き換えに、自分の時間と能力の使い方を会社に委ねることです。それは、人生の残り時間や意思決定の一部を売り渡している、とも言えるかもしれません。
もちろん、従業員と経営者が同じ方向を向いている幸福な関係もあります。しかし、基本的には両者の利害は一致しないと考える方が自然です。
だからこそ、お金を貯めることが重要になります。それは、単に贅沢をするためではありません。食べるために働くこと以外に選択肢がない状態から抜け出し、「自分の人生の残り時間をどう使うか」という選択権を、自分自身の手に取り戻すためです。能力や知識、経験というのは、その成功確率を少しでも上げるための要素なのです。
私たちが当たり前のように享受している「自由」や「人権」でさえ、実は無償で与えられているわけではありません。歴史を振り返れば、今の日本の水準で自由と安全が基本セットとして提供されることが、いかに恵まれているかが分かります。しかし、それはあくまで「基本的」な部分です。
- いつ、どこで、何をするのか
- 誰と付き合い、誰と付き合わないのか
- どんな仕事をするのか、あるいは仕事をしないという選択肢はあるのか
こうした、より能動的な「選択の自由」は、自分でお金を払って手に入れる必要があるものなのです。
4. 労働者と経営者、見える景色の違い
ここで理解しておきたいのは、労働者と経営者では、見えている景色が全く違うということです。これはどちらが良い悪いという話ではなく、根本的に違うルールに従って生きる、別の生き物だと考えた方が、認識のズレが少ないかもしれません。
経営者や資本家といった「持つ者」の側は、こうしたゲームのルールについて、あえて口にすることはありません。わざわざ話すメリットがないからです。話したところで、ほとんどの人はすぐには理解できず、行動にも移しません。リスクを取れる人はごく一部です。それならば、ルールに無自覚なまま、安定を求めて働いてくれた方が、経営側にとっては都合が良いのです。
一方で、労働者の立場から、経営者や資本家の感覚を想像するのは非常に困難です。彼らが自腹を切って事業に関わるという感覚は、実際にその立場になってみないと、本当の意味では理解できないでしょう。
つまり、労働者と経営者の間には、ゲームのルールに対する理解度に「非対称性」があるのです。経営側の方が、多くの労働者というサンプルを見ているため、労働者のことを理解しやすい傾向があります。この非対称性に、資産や資本の有無という差も加わります。
何も考えずにいると、知らず知らずのうちに、自分にとって不利なゲームに参加し続けてしまう可能性がある。この可能性を、頭の片隅に置いておいても良いのではないでしょうか。
5. 「労働者」としての時間には限りがある
もう一つ、直視しておきたい現実があります。それは、労働者として価値を発揮し続けられる時間には、ある程度の限りがあるということです。
年齢を重ねるごとに、どうしても体力や気力は低下し、仕事への出力は落ちていきます。新しい知識や技術を吸収するスピードも、若い頃と同じようにはいかなくなるでしょう。私自身、25歳、30歳、35歳、40歳と、5年刻みで体力の衰えをはっきりと感じてきました。
- 20代: 残業100時間超えも当たり前。体力と気力で押し切る働き方ができた。仕事後も勉強を続けられた。
- 35歳頃: 残業が月70時間程度になると、休日のどちらかが回復のために潰れるようになった。疲労が抜けにくくなった。
- 40代以降: 無理をしようとしても、身体がついてこなくなった。仕事後に活字を読む気力さえなくなる日も出てきた。
これは一個人の体験ですが、多かれ少なかれ、多くの人が似たような経験をするのではないでしょうか。
経営の観点から見れば、もし同じコストでよりパフォーマンスの高い若い労働力があるなら、そちらに置き換えるのは自然な判断です。また、自分が持っているスキル自体が、時代の流れとともに市場価値を失うこともあります。
つまり、自分の労働者としての価値が、今の延長線上にあり続ける保証はどこにもないのです。この前提に立って、自分は今後どのように振る舞うかを考え続ける必要があります。そう考えると、20代から30代前半の、体力・気力に満ち溢れた時期は、まさに人生のボーナスステージと言えるかもしれません。この時期にどれだけリスクを取り、学び、自分の核となる能力や考え方を磨き上げられるかで、その後の人生が大きく変わってくる可能性があります。
労働者の市場価値には賞味期限があります。その事実を忘れてはならないと思います。またAI&ロボの様な技術革新により、その賞味期限は更に短くなる可能性もあります。

おそらくここから更に技術革新により、速度が上がってゆくと思います。AI&ロボが労働市場に徐々に参入してくるということは、大きなゲーム状況の変更です。状況が大きく変わるということは、攻略方法も変わります。
過去に使えた前提や定石は、そのままでは使えなくなるかもしれません。速度も上がるので、ゲームの展開も随分あがるかもしれません。
おそらく受け身で安定を優先して対応するプレイスタイルは不利になる予感はしています。

筆者
中野 仁(Jin Nakano)
エンタープライズIT協会代表理事/AnityA 代表取締役