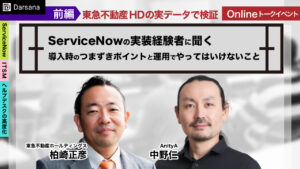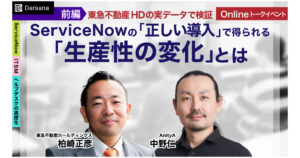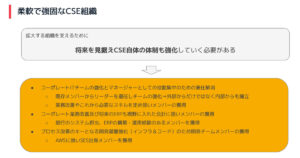苦労して書いたIT稟議書が通らない、IT投資の重要性を経営陣にわかってもらえない——。こんな悩みを持つIT部門、情シス部門の人は少なくありません。Darsanaイベントのアンケートでも、このお悩みは高い割合を占めています。
どうすればIT投資の重要性を経営陣にわかってもらえるのか、通る稟議書と通らない稟議書の違いはどこにあるのか、経営陣が通したくなるIT稟議書を作成するにはどうしたらいいのか——。 3月22日に開催したDarsana・AnityA主催のイベント「『通らないIT稟議書』は、どこに問題があるのか 経営層を納得させるためのアプローチとは」では、現役のITリーダーをゲストに招き、IT稟議が通らない理由を多角的な視点で探るとともに、その解決策を考えました。
イベントレポートの前編では、ビジネスサイドから情シス部長になったオルガノ株式会社の経営統括本部で情報システムグループ長を務める原田篤史氏と、IT出身でビジネスを学ぶことの重要性を知るIMV株式会社 IT統括部長の宮西靖氏のプレゼンテーションの模様を動画で紹介します。
オルガノ 原田氏の講演「稟議書は誰のため?経営者はどんな景色を見ているのか」
「情シス」と「情シス以外」の関係
このセクションでは、稟議書がなぜ必要なのか、という点についてお話しします。稟議書とは、経営者が責任を持ってお金を払うために必要なものであり、その仕組み自体が「クソ」なものだと、あえて最初に言っておきます。稟議書は、そもそも不要なものなら、ない方がいいと私は考えています。しかし、ないと困るから存在しているのが現状です。
稟議書が必要な理由は、複数の人が関わる組織において、全員が責任を持つためです。課長、部長、本部長、担当役員、そして社長といった関係者全員が提案内容を理解し、承認することで、初めてプロジェクトを進めることができます。このプロセス全体を理解するために、稟議書が必要となります。
海外ではこのような稟議書というものが存在しないため、この仕組みは日本独自のものといえます。
経営を知る努力をする——結局、お金を出すのは経営者
稟議書が誰のためにあるのかというと、それは経営者です。稟議書は、経営者が経営判断をするために必要なものだからです。特にIT関連の稟議書の場合、「このお金を使っていいか?」という判断材料になります。稟議が必要なのは、それを求めている人がいる、つまり経営者がいるからです。
このプレゼンテーションのタイトルは「稟議書は誰のため?経営者はどんな景色を見ているのか」ですが、なぜ私が経営について話せるのか、その背景について説明します。私は1996年に大学を卒業し、鹿島建設の子会社に入社しました。その後、転職を経験し、2007年にオルガノに入社。2017年までは水処理設備のエンジニアとして働いていたため、情報システム部門とは縁がありませんでした。
2020年、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が急務となった際、在宅勤務の体制が整っていなかったため、私が情報システム部門の責任者に就任しました。それまでITの知識はほとんどありませんでしたが、そこから必死に勉強しました。
私のキャリアの中で、海外赴任や新規事業の立ち上げを経験しました。その中で、日本の製造業の海外現地法人では、経営者的視点がなければ厳しいということを痛感しました。また、新規事業担当になった際には、何から始めればいいか分からず、とりあえずMBAの勉強を始め、そこで経営の重要性を知りました。情報システム部門の責任者になった今、部門長として経営の視点を持つことは必須だと考えています。
ゴールデンサークルでわかる、稟議書が必要な理由
稟議書が必要な理由を説明する上で、サイモン・シネック氏が提唱する
ゴールデンサークルという考え方が重要です。ゴールデンサークルは、3つの輪で構成されています。中心にあるのが「Why(なぜ)」、その次に「How(どうやって)」、そして一番外側にあるのが「What(何を)」です。
稟議書は、このゴールデンサークルの3つが揃っていないといけないと考えています。
- Why(なぜ): なぜそれをやるのか。これが最も重要であり、企業の経営理念や戦略に直結する部分です。
- How(どうやって): どうやってそれを実行するのか。これはIT部門の役割です。
- What(何を): 何をするのか。これは最終的な業務に紐づく部分です。
この3つが揃って初めて、稟議書は意味を持ちます。
長期経営ビジョンがない会社は何も提案しない方が良い
稟議書は、会社の長期的な経営戦略から紐づくものであるべきです。オルガノでは「オルガノ2030」という長期経営計画を策定しており、この計画を実現するためにIT投資が行われます。また、オルガノの経営理念は「水で培った先端技術を駆使して未来を作る産業と社会基盤の発展に貢献するパートナー企業としてあり続けます」というものです。BtoB企業であるため、この理念に個人向けのメッセージを入れる必要はありません。
長期経営ビジョンには、「昨日までのやり方を今日変える人を作る」というフレーズがあります。これは、会社が変化を続けていくことを前提としています。もし、皆さんの会社が「現状維持が目的」であるならば、何も新しい提案をしない方が良いでしょう。
稟議書は、この会社の経営理念や長期経営ビジョンに紐づいていなければいけないと考えています。
オルガノが取り入れた「3種の神器」
オルガノでは、コミュニケーションツールの
Teams、クラウドストレージのBox、そして業務改善プラットフォームのkintoneを「三種の神器」として導入しました。これらは、オルガノにこれまでなかった文化を根付かせるために導入したツールです。
- Teams: オルガノは世界中に顧客を持つため、時差や言語の壁を越えた迅速なコミュニケーションが不可欠です。メールでは時間がかかりすぎるため、リアルタイムでテキストコミュニケーションができるTeamsを導入しました。
- Box: 複数の事業部や海外拠点がある中で、顧客情報などを共有し、データを活用していくためには、ファイルサーバーではなくクラウドストレージが必要でした。Boxを導入することで、原本がクラウド上にあるという考え方を浸透させ、データ活用の基盤を築きました。
- kintone: 業務を見直すために導入しました。データに不慣れな社員でもデータに触れ、業務を改善していくきっかけとしてkintoneが適していると考えました。
これらのツールは、長期経営計画「オルガノ2030」の目標達成に紐づくものとして稟議が通されました。
経営者の視点と影響範囲・時間軸・視座の違い
経営者は、IT部門だけではなく会社全体を見ています。そのため、IT稟議書にはIT部門の都合ではなく、全社にどのような影響があるのか、顧客は誰なのかといった視点が必要です。
また、経営者はIT投資が何年持つのか、何年でペイするのか、といった
時間軸で物事を考えています。永遠に使える道具はないので、その技術がいつ陳腐化するかを考えた上で稟議書を書くことが重要です。
さらに、IT部門は費用対効果を重視しがちですが、それ以上に重要なのはWhy(なぜ)です。なぜこのプロジェクトをやるのかが明確に述べられていない限り、稟議はまず通らないでしょう。
ベンダーやコンサルタントに丸投げするのもNGです。なぜなら、その会社が何をしたいのかという
Whyは、社員しか知らないからです。社員が自社の状況を理解し、それをきちんと伝えなければ、ベンダーやコンサルタントが作成した提案書では稟議は通りません。
IMV 宮西氏の講演「IT稟議という試合に挑むために」
そもそも稟議とは?
稟議とは、組織内の意思決定プロセスの1つです。稟議のプロセスには、会社の文化が色濃く反映されます。例えば、社長決済の金額の基準や、稟議ルートの複雑さなどがそうです。歴史の長い会社では、稟議プロセスが重くなりがちですが、これを変えようとするのではなく、ルールとして受け入れた上でどう戦っていくかを考えるべきです。
稟議申請・稟議書作成のお作法を理解しよう
稟議という「試合」に挑むためには、まずそのルールを理解することが大切です。特に中途採用でIT部門に入った人は、その会社の作法に疎いことが多いので、注意が必要です。稟議規定をしっかり読み込み、規定に書かれていない社内ルールや習慣も把握しておくことが重要です。
また、決裁者が過去にどんな稟議を通し、どんな稟議を却下したのか、といった事例を研究することも役立ちます。
IT部門/情報システム部門の役割とは
IT部門の役割は、ITを活用してビジネス課題を解決し、企業価値を最大化することに尽きます。IT部門はコストセンターかプロフィットセンターかという議論もありますが、ビジネス課題の解決に貢献できるのであれば、どちらでも構わないと私は考えています。
IT部門の最終的なアウトプットがビジネス課題の解決である以上、自社のビジネスを理解せずに仕事ができるはずがありません。自社の儲けの構造や仕組みを理解しようと努めることが重要です。
地味な活動の積み重ねが効いてくる
ビジネス課題の理解と信頼関係の構築のためには、地道な活動の積み重ねが不可欠です。
- 決算資料や経営計画書を読み込む: これらは会社の方向性を理解する上での基本です。
- 事業部のメンバーのいる場所に顔を出す: 頻繁に顔を合わせることで、相手への警戒心が薄れ、ポジティブな感情を抱きやすくなります(単純接触効果)。
- 小さな宿題をもらう: 現場の小さな困りごとを解決することで、信頼を積み重ねることができます。
稟議突破力は「決裁者とIT部門の関心事」を紐付けるストーリー
「通らないIT稟議書」の問題は、稟議書の中身ではなく、稟議を出す人や組織の問題である場合が多いと私は考えます。稟議を通すためには、決裁者の関心事とIT部門の関心事を紐づけるストーリーを描くことが重要です。決裁者は会社の「計画達成」や「成長戦略」に関心がありますが、IT部門は「直近のサポート切れ」や「セキュリティ対策」など、関心事が異なる場合が多いです。この「深い溝」を埋めるためのストーリーが必要です。
稟議突破後力が重要!
稟議が通った後も重要です。稟議で上申した効果が達成されなければ、次に稟議を通す際のハードルが爆発的に上がってしまいます。稟議を単なる「打ち上げ花火」にしないためには、稟議を出す人がプロジェクトの実行まで責任を持って担当することが望ましいです。
登壇者プロフィール

オルガノ株式会社 経営統括本部 業務改革推進部
情報システムグループ長
原田篤史氏
1996年に帝京大学理工学部バイオサイエンス学科卒業後、鹿島建設のグループ会社に入社、水処理プラントの工事、設計、試運転、水質分析など水処理に関わるあらゆる業務を実施。途中1社の転職を経て、2007年にオルガノ株式会社に入社。水処理のエンジニアリング業務に従事。2013年のタイ赴任を経て、2017年に日本帰国後は新規事業や業務プロセス変革を行い、2020年3月の緊急在宅勤務の陣頭指揮を執ったことから同年7月に情シス未経験ながら情報システムグループ長に就任。以降、素人情シス部門長として、情シス部門の地位向上のために社内外で情報発信中。

IMV株式会社 IT統括部
宮西靖氏
2001年に東京外国語大学 東アジア課程卒業後、株式会社ラックに入社し、ITセキュリティ・コンサルティング業務に従事。 2004年に松下電器産業株式会社 (現パナソニック株式会社) に入社。以降、一貫して製造業のIT部門にてITインフラ構築やITを活用した業務改革に従事。株式会社クボタでの勤務を経て、2015年よりフジテック株式会社入社。ITインフラマネージャーとして、クラウド・モバイルを活用した国内・海外拠点のワークスタイル革新、CSIRT構築等を担当。 2018年よりIMV株式会社のIT部門責任者として全社のDX推進を担当。