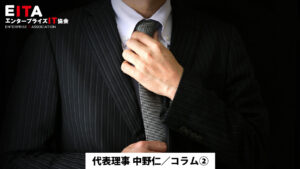まとめ
- 多くの日本企業でリーダーシップとは、ハイリスク・ローリターンな「割に合わない」役割となり、その過程は「ゴルゴダの丘マラソン」の様です。
- 一方で、波風を立てずにリスクを最小化する「そろばん勘定の最適ルート」が、個人にとっての合理的な生存戦略となっています。
- この二つの道の乖離が、まともであろうとするリーダーの「エクソダス(離脱)」を招き、組織の活力を静かに蝕んでいます。
1. はじめに:あなたはどちらの道を選ぶか?
多くの企業で「リーダーシップが重要だ」と語られます。しかし、その言葉とは裏腹に、実際にその役割を担おうとすると、多くの人が「どうも割に合わない」と感じるのが実情ではないでしょうか。
これは個人の資質の問題ではありません。むしろ、日本の組織が抱える構造的な課題が、私たちに二つの道を提示しているのです。
一つは、組織のために困難な課題に立ち向かう「ゴルゴダの丘マラソン」。
そしてもう一つは、その構造を理解し、賢く立ち回る「そろばん勘定の最適ルート」。
今回は、なぜリーダーシップが「貧乏くじ」と化してしまうのか、そして、その対極にある「最適ルート」とは何なのかを対比させながら、日本企業に横たわる根深い問題を考えてみたいと思います。
2. 「ゴルゴダの丘マラソン」- なぜリーダーシップは割に合わないのか
まず、リーダーシップを発揮しようとする者が歩むことになる、過酷な道のりを見ていきましょう。その「割に合わなさ」は、高すぎるコストと、あまりにも低いリターンに集約されます。
コスト①:当事者意識のない人々から石を投げられ続ける
日本の組織は階層主義と合意形成を重んじます。これは丁寧なプロセスである一方、リーダーにとっては凄まじいコストを強いることになります。
- 終わらない根回し: 上下左右の全部署に話を通す必要があり、調整と説明だけで膨大な時間が奪われます。
- 集中砲火を浴びる立場: 当事者意識のない人々から、それぞれの立場での意見や批判がリーダー一人に集中します。まさに、四方八方から石を投げつけられながらゴルゴダの丘をマラソンするような感覚に陥るのです。
- コミュニケーションコストの倍々ゲーム: 取引先も同様の文化を持つことが多く、社内と社外の調整でコミュニケーションコストは雪だるま式に膨れ上がります。
使命感や職業倫理だけで滅私奉公していても、この終わりなきマラソンにウンザリした時、リーダーの心は折れてしまいます。
コスト②:権限なき責任と、挑戦を罰する評価制度
これだけの手間と精神的負担をかけても、得られるリターンは驚くほど小さいのが現実です。
- 権限なき無理難題: 十分な予算や権限が与えられないまま、経営層から大きな課題が丸投げされます。
- 際限なく広がる責任範囲: 各部署からは「これもやってよ」と次々と仕事が投げ込まれ、責任だけが肥大化していきます。
- 減点主義の罠: 最も深刻なのが、評価が減点法であることです。たとえ結果が良くても、プロセスで強引な進め方をすれば「和を乱した」と評価が下がり、失敗すれば大きな減点を食らいます。
挑戦には常に失敗のリスクが伴いますが、そのリスクに見合うリターンはなく、むしろペナルティの方が大きい。これが、「ゴルゴダの丘マラソン」の実態です。
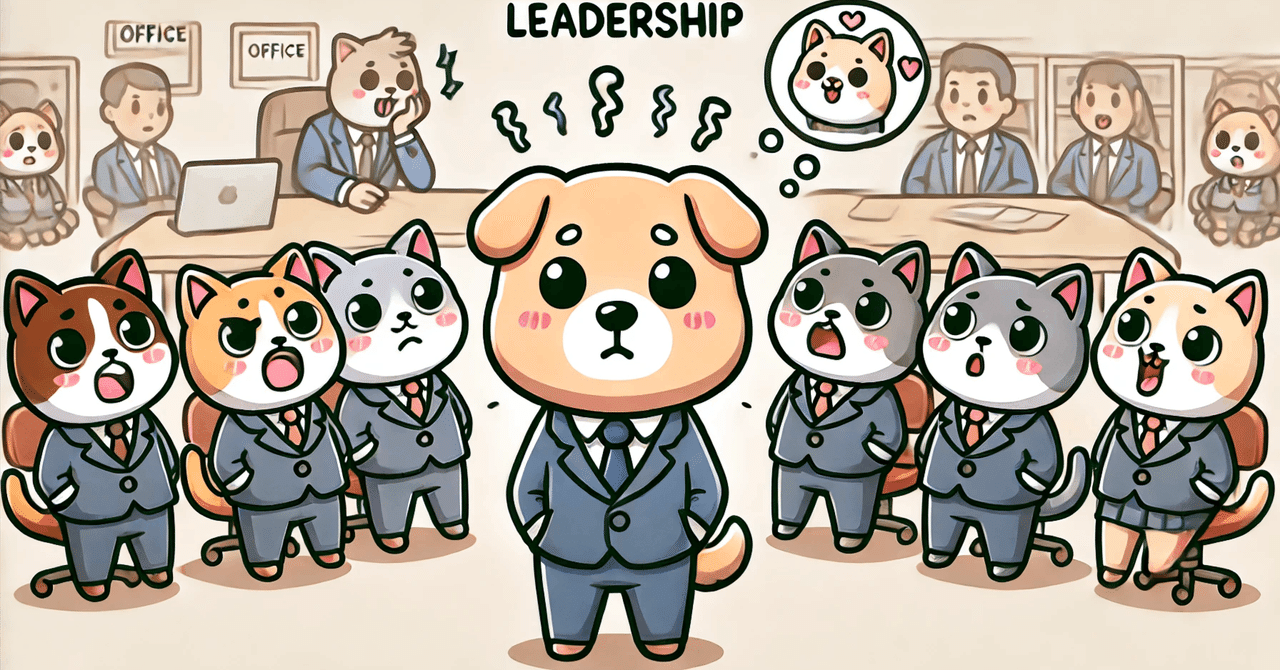
3. 「そろばん勘定の最適ルート」- 日本企業の会社員としての最適な道
さて、前述のような「割に合わない」構造を目の当たりにしたとき、個人にとって最も合理的で賢明な選択、すなわち「そろばん勘定の最適ルート」とは何になるのでしょうか。それは、まともであろうとする人たちの道とは真逆の、リスクを徹底的に回避し、安定を確保するという生存戦略です。
最適ルート①:「旗を持たない」という選択
まず、社運をかけたプロジェクトのような、目立つ「旗」は自ら持たないことが鉄則となります。旗を持てば、矢面に立たされ、石を投げられるのは目に見えています。火中の栗を拾うような真似はせず、そうした案件とは適切な距離を保つのです。
最適ルート②:「改善」と「おもてなし」レベルに留める
大きな変革を目指すのではなく、自分の手の届く範囲で、関係者をうまく巻き込みながら小さな「改善」を積み重ねて「技あり」を取り続ける。これが、多くの賢者が実践する立ち回りです。
「改善」は、損をする人が少なく、誰かから恨みを買うリスクも比較的低いため、そろばん勘定に合います。会社や顧客の「本当の未来」といった大きな話には深入りせず、まずは他部門との関係性を悪化させない範囲で、手堅く自分の評価を積み上げることを優先するのです。
和を大切にするには、他部門のひんしゅくを買う事をさけ、感謝される事を最優先にしなければなりません。会社全体の利益は経営が考えることです。自らのポジションと自部門の防衛こそ最優先です。そのためには他部門に感謝される「おもてなし」が大切です。
最適ルート③:「やっている感」の演出
もちろん、何もしなければ評価されません。そこで重要になるのが「やらないと流石に怒られるので、やっている感を出す」という立ち回りです。会議では的を射た(ように見える)質問をし、資料は丁寧に作り込む。しかし、決して組織のタブーに踏み込んだり、誰かの縄張りを荒らすような提案はしません。
和を乱して突出するなんてもってのほかです。他部門・メンバーから的にされ、経営・上司から梯子外しを食らうリスクは最小化しなけばなりません。会社員の最大の報酬は労働法に守られた安定と安全なのですから。その対価としての源泉徴収と累進課税なのです。対価を払ったサービスは最大限活用しなければなりません。
これが、多くの日本企業において、会社員が自らのキャリアを守り、安定した生活を送るための、極めて合理的で賢い「最適ルート」なのです。
4. 「最適ルート」が招く、組織負債の増加
しかし、組織に属する多くの人がこの「そろばん勘定の最適ルート」を選び続けた結果、組織全体としてはどのような事態に陥るのでしょうか。
リーダーの「エクソダス」と、コンサルへの依存という悪循環
ゴルゴダの丘マラソンに疲弊したリーダーが、ついに会社を去る「エクソダス」が発生します。特に多いのが、その能力を高く評価してくれるコンサルティングファームへの転職です。
- インセンティブの圧倒的な差: 事業会社では責任だけが増え報酬は上がらない一方、コンサル業界ではシニアは1人あたり月200〜300万円といった高額な単価で評価されることも珍しくありません。この報酬格差の前では、事業会社が優秀な人材を引き留めるのは困難です。
- しかし、労働市場の価格では、本来リーダーシップが伴う仕事はそれくらいの価値がつくものなのではないでしょうか?リスクを考慮したとしても事業会社の待遇がそれを反映できていない可能性はあります。
- リーダーシップの外注化と、負のスパイラル: 社内リーダーを失った企業は、その穴を埋めるために外部のコンサルに依存するようになります。ここに、自社で育てた人材をコンサルに奪われ、その人材をコンサルフィーという高値で借り戻すという、皮肉な悪循環が生まれます。事業会社が負担した育成コストはコンサル企業に吸収され、企業はさらに高額な費用を支払い続けることになるのです。失敗した時も正社員と違ってベンダーは切れば良く、戦後処理が比較的楽なのも人気の理由ではないでしょうか。
- 「貧乏くじ」認識の伝染とエクソダスの連鎖: さらに深刻なのは、リーダーの離職によって、その人が担っていた役割が「貧乏くじ」であるという認識が社内に知れ渡ることです。そうなると、ますます社内で手を挙げる者はいなくなり、コンサルへの依存度は高まる一方です。

静かに蓄積される「組織負債」
この悪循環の末路は、事業会社の企画推進能力そのものの低下です。各現場が部分最適(=改善)を繰り返し、全体を俯瞰するリーダーシップが外部に委託されることで、組織は徐々に空洞化していきます。
やがて、自社の施策の見積もりすらできなくなり、コンサルの指示なしにプロジェクトを推進できない企業体質へと変貌を遂げます。企画・導入・運用すべてを外注し、自社のビジネス戦略すらコンサル頼みになる。これは、競争力の源泉を自ら手放すことに他なりません。
自らの企画推進力もなく、ベンダーとの調整・発注業務という作業に追われ、謎に参加人数が多い打ち合わせでスケジュールがテトリスになっているみたいな状態の組織では、社内の課題解決はもちろん、外部のコンサル・エンジニアとも適切に仕事をすることもできないのではないでしょうか。
内部が弱体化し過ぎると外部としっかりとした仕事ができなくなります
失敗したプロジェクトを分析した時、ベンダー側は頑張っているのだけど、発注側の組織が弱すぎて失敗したみたいな話は結構な頻度であります。もちろんそれを語る事にインセンティブがないので、世の中は「成功プロジェクト事例」という大本営発表で満ちています。
ユーザー側は「ベンダーが駄目だったので失敗しました」という説明を作る為にも外部を使うメリットはあります。そして、ベンダー側は一定そういう事が起こることを理解して、価格に乗せ予防線を貼る訳です。
こうして、気づかぬうちに技術的、あるいは組織的な負債が蓄積され、「自社のことが分からず外部に頼る企業」になってしまうリスクが高まるのです。
5. なぜ「最適ルート」はやめられないのか
会社員という立場である以上、「そろばん勘定の最適ルート」を選ぶことは、極めて自然なことです。
最大のペナルティが「解雇」で、最大のリターンが「出世・ボーナス」というゲームのルールにおいて、既存事業を否定するような新規事業の立ち上げや、同僚の恨みを買うリストラの断行といったハイリスクな仕事は、どう考えてもリターンに見合いません。
もし運良く修羅場を乗り越え役員になったとしても、手にする報酬がその苦労に「本当に割に合ったか?」と問われれば、多くの人が疑問を感じるでしょう。だからこそ、「リスクはそこそこに抑え、確実かつ長く利益を得られる選択肢」、すなわち「最適ルート」を選ぶのです。
本当に大きな賭けに出て不退転の覚悟で物事を進められるのは、自分の資本を投下しているオーナー社長くらいなのかもしれません。
6. それでも「まともであろうとする人たち」が報われる組織であるために
これまで見てきたように、日本企業におけるリーダーシップは、多くの場合、個人の自己犠牲の上に成り立っています。そして、その他大勢は、その試みを横目に「そろばん勘定の最適ルート」を実践し、安全な場所からその他人のリーダーシップを消費することで、組織はかろうじて延命しているのです。
しかし、割に合わないとわかっていながらも、強い矜持や問題意識に突き動かされ、茨の道を歩もうとする**「まともであろうとする人たち」**は、どの組織にも必ず存在します。
彼らが、単なる「インテグリティの殉教者」(誠実さや責任感ゆえに、報われないと知りながらも組織のために困難な役割を引き受け、結果的に消耗し使い潰されてしまうこと)で終わり、疲弊の果ての「エクソダス」につながってしまう組織は組織負債により競争力を減衰させてゆきます。
大切なのは、「そろばん勘定の最適ルート」が唯一の正解ではないと組織が自覚し、リスクを取ってでも挑戦する人が報われる仕組みと文化を築くことでかもしれません。
まともであろうとする人たちの道が、いつか最適ルートと並び立つ、あるいはそれ以上に魅力的な選択肢となること。それこそが、長期的に組織が前に進むための方法となるのではないでしょうか。
結論
- 多くの日本企業では、「ゴルゴダの丘マラソン」と「そろばん勘定の最適ルート」という二つの道が明確に分かれています。
- 個人が合理的な「最適ルート」を選び続ける限り、組織は静かに活力を失い、組織負債が蓄積されていきます。
- まともであろうとする人たちが報われる仕組みを整え、「割に合う」リーダーシップを実現することが、企業の未来にとって必要ではないでしょうか。
この内容を元に各種データを参照にした記事はこちらです。

筆者
中野 仁(Jin Nakano)
エンタープライズIT協会代表理事/AnityA 代表取締役