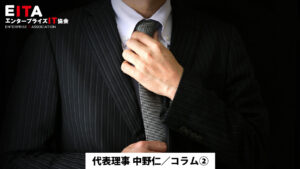まとめ
- 日本のスタートアップは、国内市場への最適化の結果、特定の事業領域に集中し、同質化しやすい構造の中に置かれていることがあります。
- この状況は、AIによる競争環境の変化や日本特有の商習慣を背景とした、短期的な収益性を追求する上での合理的な選択ともいえます。
- 大切なのは善悪で判断するのではなく、この「ゲームのルール」を理解し、創業者、従業員、投資家それぞれが賢く立ち回ることではないでしょうか。
1. 「最近、スタートアップはどう?」–– 聞こえてきた、ある種の閉塞感
始まりは、ふとした雑談から
先日、知人と「最近のスタートアップってどうなんだろう?」という話になりました。2022年頃から、世界的な金利上昇を背景に投資マネーが市場から引き上げられ、スタートアップにとって厳しい状況が続いているという話は以前から耳にしていました。しかし、少し深く話を聞いてみると、課題は単なる資金調達の難しさだけではない、より根深い構造にあることが見えてきました。
世界に目を向ければ、アメリカや中国がAIやロボティクスの分野で、未来をかけた熾烈な競争を繰り広げています。一方で、日本のスタートアップ業界は、少し違う様相を呈しているようです。多くの場合、日本のローカルな法律や独特の商習慣の隙間を埋めることにビジネスチャンスを見出しているというのです。
その結果、事業モデルが特定のパターンに収斂しやすい傾向がある、という話でした。具体的には、以下のようなものです。
- ① 部分最適のSaaS:
- 特定の業界だけで使われる複雑な請求書形式や、日本独自の雇用慣行など、ニッチな課題に対応するソフトウェア。
- ② デジタル人材派遣・紹介業:
- SaaSという看板を掲げながら、実態は特定のスキルを持つ人材を顧客企業に常駐させ、その対価を得るビジネス。
- ③ デジタル問屋業:
- 他社のSaaS製品を仕入れ、自社のコンサルティングなどと組み合わせて販売する代理店ビジネス。
もちろん、これらのビジネスが社会の課題を解決し、価値を提供していることは間違いありません。しかし、業界全体がこうした特定のビジネスモデルに集中しているとしたら、それは少し気がかりな状況です。
微かに感じる「治安の悪化」
さらに、「おまけに、事業とは直接関係のない仮想通貨の保有で企業価値が変動したり、残念ながら粉飾決算のような事案が起きたりすると、『この業界に投資したり、身を投じたりするのはどうなのだろう…』という雰囲気が生まれてしまうのも、無理はないのかもしれません。短期的な成功を焦るあまりガバナンスが疎かになるケースが増えるかもしれない」といった懸念の声も聞こえてきます。
こうした会話をきっかけに、今のスタートアップが置かれている状況とその背景にある構造について、少し深く考えてみたいと思います。
2. AIが変えた競争のルール –– 技術で差がつかない時代の戦い方
「作る」ことの価値の変化
一昔前まで、優れたシステムをいち早く開発すること自体が、企業の大きな競争力になっていました。しかし、GitHub Copilotのようなコーディング支援ツールや、各種生成AIのAPIが普及したことで、開発効率は飛躍的に向上しました。誰でも高度なツールを使えるようになった結果、皮肉なことに、システムそのもので他社と差別化を図ることが、以前よりも格段に難しくなっているのかもしれません。
では、どこで差がつくのでしょうか。多くの企業が同じ結論に至るように、その答えはシステムの外側に求められがちです。それが、顧客の業務オペレーションそのものを丸ごと請け負うBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のようなサービス、いわゆるBPaaS(Business Process as a Service)と呼ばれる領域です。
しかし、これもまた、新たな厳しい競争の始まりに過ぎません。考えることは皆同じなので、似たようなサービスが市場に溢れ、価格競争に陥りやすくなります。
資本力がものを言う戦場へ
結局、多くのケースで行き着く先は、マーケティングと営業による激しい顧客獲得競争や、人海戦術です。潤沢な資本を背景にした大規模な広告展開や、営業人員の大量採用といった、いわば「札束の殴り合い」で勝利するかどうかが問われるようになっていくのではないでしょうか。
また、AIをこれまでITとは無縁だったアナログな業界に導入しようとすると、話は簡単ではありません。そこでは、AIの導入を大前提とした業務プロセス全体の再設計という、非常に難易度の高い取り組みが不可欠となります。この時に求められるのは、経営層を巻き込みながら複雑な課題を整理し、組織全体で粘り強く実行し続ける高度な組織力です。しかし、多くの企業にとってこれを自前でやり遂げるのは容易ではありません。
このように、AIの登場によって、ビジネスの主戦場はシステム開発そのものから、営業、マーケティング、コンサルティング、運用代行といった、潤沢な資本力がものを言う領域へと静かに移りつつあるのかもしれません。
3. 「デジタルJTC」という現象 –– 新しい皮を被った古いモデル
現実的な出口としての「売却」
ビジネスの主戦場が資本力勝負の領域に移っていく中で、企業の最終的な出口戦略として、大手企業への事業売却というシナリオが現実的な選択肢として強く意識されるようになっているように感じます。しかし、買い手である大手企業も、以前のような楽観的な価格で買収することはなくなり、創業者や初期の投資家以外の従業員が得られる恩恵は、ますます限られたものになってしまいます。
薄皮を一枚めくれば…
ここで、ある厳しい指摘が頭をもたげます。それは、「『俺たちは新しいことをやっているスタートアップだ』と言っても、そのデジタルという薄皮を一枚めくれば、かつて旧態依然として批判していた日本的な大企業(JTC)と、ほとんど同じビジネスモデルではないか」というものです。
違いといえば、
- 平均年齢が少し若い
- オフィスがお洒落な雰囲気である
- 服装が自由で、コミュニケーションにSlackを使っている
といった表面的な部分だけで、事業の本質は結局、代理店業や人材業だったりする。「おかしいとは思う。でも、SaaSで毎月少しずつ利益を積み上げるより、代理店業や人材業の方が手堅く、すぐにまとまったお金が入ってくるんだよね…」と、あるスタートアップ経営者が本音を漏らしていたという話も、一度ならず耳にしたことがあります。
この、いわば「小さなデジタルJTC」とも呼べる現象は、なぜ生まれるのでしょうか。
4. なぜ「日本仕様」から抜け出せないのか? –– 合理的な選択の帰結
「おもてなし」が産んだジレンマ
「デジタルJTC」化の背景を考える上で、日本市場の特性は無視できません。日本の顧客は、画一的なサービスよりも、自社の細かい要望に応えるためのカスタマイズや、手厚いサポート体制といった「おもてなし」を求めがちです。
この「顧客に寄り添う」姿勢は、SaaSが本来持つ「一つの製品を多くの顧客に安価に提供する」というビジネスモデルと、本質的に相性が良くありません。結果として、顧客ごとの個別開発が増え、「実質的なSIer(システムインテグレーター)」のようになってしまうのです。
このような日本国内の市場環境に最適化して勝ちパターンを構築するほど、海外で通用するような汎用的なサービスやビジネスモデルからは遠ざかってしまうのです。つまり、国内市場で手堅く収益を上げることを考えた場合、現状のビジネスモデルに落ち着くのは、ある意味で非常に合理的な経営判断と言えるのです。
軽蔑していたはずの相手に
スタートアップ界隈では、日本企業の保守性・アナログさを「JTC」として揶揄する風潮が以前からあります。しかし、そのJTCこそが海外で稼ぎ、日本の雇用を支えているという現実もあります。
最も皮肉なのは、JTCを軽蔑していたはずが、「気がつけば自分たちも同じ姿になっていた」と絶望することです。理想を追い求めていたはずが、日々のオペレーションや資金繰りに追われる中で、いつの間にか最もなりたくなかった姿になってしまう。この構造的なジレンマが、多くのスタートアップを悩ませているのかもしれません。
以前からある日本企業を「JTC」と嘲笑するスタートアップの傾向が、翻ってみると自分たちも大差ない。むしろ海外進出をして雇用を生み出しているのは伝統的な日本企業の方であるという矛盾を多くの人が理解して、キラキラ感が色褪せてしまっているのかもしれません。
5. 「売り抜けるつもりでしょう?」–– 創業者と従業員の間に生まれる溝
こうした状況は、創業者と従業員の間に微妙な、しかし深刻な溝を生み出している可能性があります。「デジタルJTC」の実態が透けて見えると、創業者たちが語る「世界を変える」といった壮大なビジョンが、どこか虚しく聞こえてきてしまうのです。
そして、事業売却という出口戦略が現実味を帯びてくると、従業員や外部からは「でも、あなた達も、最後は売り抜けるつもりでしょう?」という冷めた視線が向けられるようになります。
この本音と建前、言っていることとやっていることの乖離が、組織に様々な問題を引き起こします。優秀な人材が実態とのギャップに失望して離れていったり、社内の士気が低下したり、短期的なKPI達成への過度なプレッシャーが蔓延したりするのです。
もちろん、創業者側にも事情はあります。問題は、その現実と、従業員に語られる建前との間に大きなズレが生じていることなのかもしれません。
最後に:私たちはこの現実とどう向き合うべきか
この構造は、短期的な利益や国内市場での安定を考えれば、ある意味で非常に合理的な選択と言えます。だからこそ、この流れがすぐに変わることはないでしょう。
大切なのは、この現状を「良いか悪いか」で評価するのではなく、まず「そういうものだ」という現実として受け止めることかもしれません。
その上で、創業者、従業員、投資家がそれぞれの立場で、このゲームのルールを理解し、自分にとってのリスクとリターンを冷静に見極める。大きな理想を語る前に、まずは目の前の現実に向き合い、賢く立ち回ることが求められているのではないでしょうか。
- 創業者は、事業モデルの持続可能性を冷静に見極め、従業員に対して誠実なコミュニケーションを心がける。お金や人を集める為だけで実現する気が無い大風呂敷は控え、困難さやデメリットも語る様にする。
- 従業員は、企業のビジョンだけでなく、ビジネスモデルや収益構造を理解し、自身のキャリアプランと照らし合わせる。キラキラしたマーケ・広報を過度に信用しない。
- 投資家は、表面的な成長率だけでなく、事業の本質的な競争力や組織文化を見極める。手堅く成長するとわかってる企業ならばエクイティで資金調達する必要はない。
結局のところ、特効薬はありません。それぞれのプレイヤーが、この複雑な現実を直視し、自らの頭で考え、行動していくことが、閉塞感を打ち破る唯一の道なのかもしれません。
筆者
中野 仁(Jin Nakano)
エンタープライズIT協会代表理事/AnityA 代表取締役