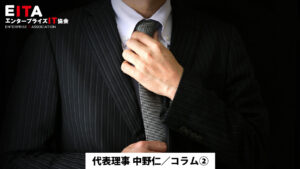まとめ
- スタートアップは、正社員のような安定性を求める人が安易に行く場所ではないかもしれません。
- 従業員として働くのであれば、自身が取るリスクに見合ったリターンが得られるのかを冷静に考えることが大切です。
- 会社の広報やマーケティングが発信するキラキラした情報を鵜呑みにせず、その裏にある実態を見抜く視点を持つことが求められます。
1. はじめに:スタートアップへの幻想と現実
「スタートアップ」と聞くと、革新的なサービス、自由な働き方、そしてストックオプションによる一攫千金といった、華やかなイメージを思い浮かべる人も少なくないかもしれません。メディアで取り上げられる成功事例は、私たちの期待を膨らませます。
しかし、その一方で、スタートアップで働くことは、本質的に高いリスクを伴う選択であるという側面も存在します。外から見えるキラキラした姿は、IR(投資家向け広報)やマーケティングによって巧みに作られたものである可能性も十分にあります。
この記事では、スタートアップという選択肢を考える際に、一度立ち止まって冷静に考えてみたい論点について、掘り下げていきたいと思います。特に、従業員としてスタートアップに関わることを検討している方にとって、後悔のない選択をするための一助となれば幸いです。
2. スタートアップはどのような人に向いているのか?
では、どのような人がスタートアップという環境で力を発揮しやすいのでしょうか。
一つの考え方として、スタートアップは「ある程度資産を貯め、実力もついた即戦力のシニアが一発当てるためにいく場所」という見方があります。これは、スタートアップが安定した雇用を約束する場所というよりは、個々の実力と貢献が直接的に結果に結びつく、固定給がでる業務委託のような認識に近いかもしれません。
経営者はもちろんのこと、参加するメンバーも相応のリスクを取る覚悟が求められます。スタートアップは、調達した資金を燃やし、事業の成長速度を上げて走る中小企業とも言えます。資金を燃やし尽くす前に事業を軌道に乗せるという、時間との勝負をしているわけです。そのため、本質的に余裕はなく、常に切迫感と緊張感が漂っています。
このような環境は、まるで競馬場のようです。資本家が莫大なお金を投入し、馬の代わりに人が走る訳です。一発逆転を狙う面白さがある一方で、誰もが勝者になれるわけではありません。そのスリルとリスクを楽しめるくらいの気概がなければ、厳しい現実を目の当たりにすることになるかもしれません。
少なくとも安定を求める人はまったく向いてないのではないかと思います。会社を辞めても直ぐに次を見つけられるというくらいの見通しを持てる人でないと厳しいのではないかなと。
3. なぜ多くの人にとってスタートアップは「場違い」になりうるのか?
もし、あなたが会社に対して正社員としての安定性を求めるのであれば、少なくとも上場前のスタートアップに入るのは、ミスマッチになってしまう可能性があります。
3-1. ジュニア層が直面しやすい現実
特に、まだ社会人経験の浅いジュニア層にとっては、より慎重な判断が求められます。
スタートアップが少し資金調達をすると、事業拡大のためにジュニア層を採用する光景がよく見られます。しかし、会社側の主な目的が「安い労働力」の確保であるケースも少なくありません。事業をスケールさせる段階では、思考力よりもまず行動量が求められる場面があり、その担い手としてジュニア層が期待されるのです。
しかし、ここには注意が必要です。従業員側からすると、頭を使わずともこなせる作業に近い仕事を膨大にこなしても、身につくのは「作業員の能力」になってしまう恐れがあります。本当に会社に貢献できるスキルや、市場価値の高い専門性が身につかないまま時間だけが過ぎていくのです。そして、もし会社の経営が傾き、お仕事がなくなってしまった時、「あなた自身の力で次の道を見つけられますか?」という問いに、胸を張って「はい」と答えられない状況に陥る可能性があります。
日本にはまだ「新卒カード」という独特の価値が存在します。良いカードを切れるのであれば、そのカードでしか入れない会社も世の中にはたくさんあります。実力さえあればスタートアップにはいつでも挑戦できるかもしれませんが、新卒でしか得られない機会を安易に手放すのが、本当に投資対効果として妥当なのかは、よく考える必要があるでしょう。
3-2. 安定志向の人が抱えやすい不幸
スタートアップは、本質的に資本主義ゲームでレバレッジを効かせた博打をしている組織です。資金調達で得たお金を燃やして、速度を上げて走るため、カーブを曲がりきれずに事故を起こしたり、ガス欠で止まってしまったりすることも珍しくありません。
このような組織に、安定を求めて入社してしまうと、本人も会社も不幸になる可能性があります。フリーランスが正社員のスタンスで仕事を受けると上手くいかないのと同様に、スタートアップに正社員の安定感を求めてしまうと、そのギャップに苦しむことになるでしょう。
日本の労働法は、雇用の安定を重視する側面が強いですが、常に変化し続けるスタートアップの事業環境とは、必ずしも相性が良いとは言えないのかもしれません。
4. 「キラキラ広報」の裏側を見抜く目
スタートアップを取り巻く情報には、注意深く接する必要があります。特に、広報やマーケティング、経営者のポジショントークを鵜呑みにしてはいけません。
これらの情報は、主に投資家や顧客に向けて発信されているものです。事業の成長性や魅力を最大限にアピールするために、ポジティブな側面が強調されるのは当然のことです。時には、数字を最大化するために、レイオフのニュースですらマーケティングに活用するのが、何でもありのスタートアップの世界なのかもしれません。
しかし、自分の生活をかけて働く労働者が、そのキラキラした情報に釣られてしまうのは、あまりにもリスクが高いと言わざるを得ません。提灯記事を読んで鵜呑みにするような人は、一つのミスが大きな影響を及ぼしかねないスタートアップで、重要な仕事を任せるのは難しいと判断されても仕方がないかもしれません。このくらいの情報の評価ができないならば、スタートアップに行くには経験値が足りないかもしれません。
5. リスクとリターンを天秤にかけるということ
では、従業員としてスタートアップに参加する場合、どのような視点を持てば良いのでしょうか。それは、自身が取るリスクに対して、リターンが見合っているかを冷静に考えることです。
経営者は、フルレバレッジをかけた結果として、上場や事業売却に成功すれば、人生が大きく好転するほどの資本を手に入れることができます。しかし、従業員、特にメンバー級で関わる場合、得られるリターンはどれくらいなのでしょうか?
例えば、会社の出口戦略(IPOやM&A)が成功した際に、サイドFIRE(経済的自立と早期リタイア)が見えるくらいのリターンがなければ、大きなリスクを取る価値は低いと考えることもできます。
特に、会社がある程度の規模(例えば50人〜100人超)になった中途半端なタイミングで労働者として加わると、リスクとリターンのバランスが微妙になりがちです。これは、何を隠そう、筆者自身が過去に経験したことでもあります。
スタートアップで働くということは、自分が参加しているゲームのルールをよく知らないまま、危険な場所に参加するようなものです。スタートアップ界隈は競馬場の様なもので自己責任の色が濃いです。リスク管理は当然自分の判断でする必要はあります。失敗して自分に損害がでて他人のせいにしたいならば向いてないかもしれません。他人のせいにしても良いですが基本的に無視されます。
6. 「安定したベンチャー」という選択肢の罠
中には、「急成長するスタートアップはリスクが高いけれど、ある程度安定したフェーズのベンチャーなら良いとこ取りができるのでは?」と考える人もいます。確かに、そこそこの規模のベンチャーは居心地が良いと感じるかもしれません。
しかし、「安定したベンチャーは大手とスタートアップのいいとこ取り」という話は、裏を返せば「悪いとこ取り」にもなりうる、ということを忘れてはいけません。
- スピード感と報酬のアンバランス:事業のスピードが速く忙しい一方で、報酬は外資系企業には及ばない。
- 求められるリーダーシップの不均衡:大手企業とは異なる性質のリーダーシップが求められる割に、権限や報酬が見合わない。
特に中間管理職の立場になると、この「割に合わない問題」に直面しやすくなる可能性があります。面白い仕事ができるわけでもなく、大きな資産を築けるわけでもない、という微妙な状況に陥ることも考えられるのです。
7. 結論:ゼロリスクの安全圏はどこにもない
ここまで、スタートアップで働くことのリスクについて述べてきました。では、大手企業なら絶対に安全なのでしょうか。
答えは「いいえ」です。
大手企業は、自己責任の度合いを低くできるかもしれませんが、ぼんやりと過ごしているうちに能力が身につかず、歳をとってから放り出されるリスクは常にあります。会社の経営が本当に厳しくなれば、大手企業であっても人員整理は行います。そのやり方も、子会社への出向を経て報酬を下げ、退職に追い込むなど、一見すると分かりにくい形で行われることもあります。大企業はコンサルを雇い、労働法を回避し、会社の評判を極力下げない為に芸術点が高いレイオフ手法を編み出し実行します。
結局のところ、スタートアップであろうと大手企業であろうと、ゼロリスクの安全圏など存在しないのです。
大切なのは、自分がどのような人生を歩みたいのか、どれくらいのリスクなら許容できるのか、そしてそのリスクに見合うリターンは何なのかを、常に自分自身の頭で考え、天秤にかけることです。そして、その判断に基づいて主体的に決断し、行動し続けること。それこそが、AI&ロボで荒れ模様と予測される明日を生き抜くために、最も重要なスキルなのかもしれません。
結論
- スタートアップは、会社というよりは、リスクを取ってリターンを狙う「プロジェクト」に近い性質を持っています。
- どのような組織で働くにせよ、リスクが全くない安全な場所というものは存在しません。
- 自分自身のリスク許容度と優先事項を常に天秤にかけ、主体的に判断し行動することが何よりも重要です。
筆者
中野 仁(Jin Nakano)
エンタープライズIT協会代表理事/AnityA 代表取締役