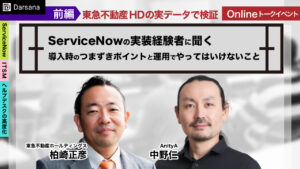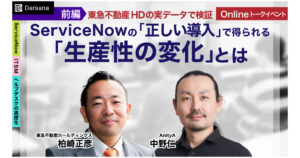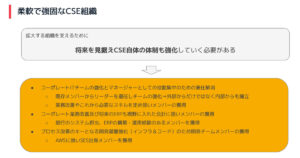コロナ禍を契機に、これまでにも増してDXの機運が高まっています。IT部門にとっては大きなチャンスであり、このムーブメントを企業の成長に生かさない手はありません。ただ、このチャンスを最大限、生かすためには、「自社にとってのDXの意味」を考え、「その中で自分が果たすべき役割」を明確にする必要があります。
DXとはいったい、どのような未来を実現するための取り組みなのか、それを実現するために、企業のIT部門、ITコンサルタント・SIer、プラットフォーマーは、それぞれどのような考えのもと、どのような役割を果たしていけばいいのか──。
本記事では、AnityAが開催したイベント「またとない変革の好機『DX祭』の波をどう乗りこなすか 武闘派CIOの友岡氏と考える会」の模様を動画でご紹介します。
後編では、武闘派CIOとして知られるCIO Loungeの友岡賢二氏、日本マイクロソフトのクラウド&ソリューション事業本部でセキュリティ分野を担当している山本築氏、AnityA代表取締役の中野仁の3人が参加者から寄せられた質問に回答する模様を動画でお送りします。
動画インデックス
・Q&A
-Q1【00:00:46】
全社DX推進が始まり半年経過したものの、事業部門が受け身の状態。より一体感を持ってDXを推進するための仕掛けや取り組みについて、ぜひアドバイスを頂きたい。
-Q2【00:06:09】
いろいろな解釈があるDX。登壇者の考えるDXについてお聞きしたい。
-Q3【00:09:57】
今後、IT部門に求められる役割やケイパビリティは何か?
-Q4【00:11:25】
DX推進は「全社プロジェクト」であり、社員一人一人のマインド変革がスタート地点だと思っている。フジテックはどこからDXをスタートしたのか?
-Q5【00:20:21】
SIerへの丸投げから、事業会社で戦略・企画を考え、内製化に向かう仕組みへと移行している。それを進めるうちに、出入りのSIerやほとんどのIT企業からの提案がまったく役に立たなくなった。こうした中で、共創できるIT企業やパートナーを探すにはどうしたらいいのか。
-Q6【00:27:28】
「何が必要か」を考える「SI営業的な思考」を育てる必要があるというのはまさしくその通りだと思うが、社内で話しても理解されない。どうしたらいいか。
-Q7【00:27:57】
「Before ITわからない経営層の人 → After IT興味ある経営層の人 の変身/クラスチェンジ(同一人物)」は実在する現象なのか? もし実在するなら、どういうきっかけで起こるものなのか?
-Q8【00:30:56】
経営層のみならず会社全体としてのITリテラシー、データリテラシーのあり方についての見解をお聞きしたい。この点について海外企業との違いについても何かあればお聞きしたい。
-Q9【00:37:01】
営業サイドが強引に放り込んだまま機能しなくなっている社内案件があったとき、CIO的には敗戦処理となるが、どこから手をつけたらいいか?
-Q10【00:40:18】
データ分析部門として、社内の事業部とコラボレーションして、データ分析を推進しているが、なかなか成果につながらない。パッションを失わずに走り切るためのアドバイスをいただきたい。
まとめ
DX推進における課題と解決策
DXの推進において、参加者からは様々な悩みが寄せられました。特に、DXの推進が形骸化している、事業部門が受け身になっているといった課題が浮き彫りになりました。
- DXの形骸化
- 課題: DXを推進すると言いながら、実際はシリコンバレーにオフィスを作ったり、銀座にコワーキングスペースを設けたりといった形から入る「なんちゃってDX」に陥りがちです。また、DXを推進することが目的化してしまい、本来の事業や顧客から離れた場所で議論が交わされることも問題視されています。
- 解決策: 重要なのは、事業そのものに焦点を当てることです。DXはツールを入れることではなく、顧客との関係をどうするか、事業をどう強くするかを考えるための手段です。DX推進部門は、事業部門に入り込んで顧客について深く理解し、事業をどうすればより良くできるかを考える必要があります。
- 事業部門の受け身な姿勢
- 課題: 事業部門が受け身で、DX推進部門が主導権を握ってしまい、なかなか一体感が生まれないという声がありました。
- 解決策: まず、小さな成功事例を積み重ねていくことが大切です。例えば、カレンダーの空き時間設定など、従業員の身近な業務習慣が変わるような小さな変化から始めると良いでしょう。そういった小さな成功を可視化することで、従業員の意識が変わり、モチベーション向上につながります。
意思決定の質を高める
海外企業と比較して、日本の企業では意思決定のサイクルに課題があることが指摘されました。
- 課題: 多くの日本企業では、データ活用やDXを推進しようとしても、意思決定のサイクルが週次、月次といった長いスパンで行われており、リアルタイムなデータ分析が活かされにくいという現状があります。
- 解決策: 意思決定の質を高めるためには、**「現場で現物を見ながら現実はどうなのかを確認し、判断していくこと」**が重要です。どのデータをどのように見せるべきかを考え、経営層がリアルタイムで事業の状態を確認できる仕組みを構築することが、健全な議論につながります。
マインドセットの重要性
DXを推進するIT担当者が抱える悩みに対し、マインドセットに関するアドバイスが送られました。
- 「心折れずに頑張り続けるにはどうすればいいか」
- アドバイス: 会社全体の大きな問題に悩むのではなく、自分が責任を持って変えられる範囲の小さなことに集中することが大切です。例えば、「今日は昨日より少し進んだ」「来週は今週より良くなる」といった小さな変化を実感できれば、モチベーションを維持できます。
- 「上司や他部門に丸投げされる」
- アドバイス: できないことや権限のないことに悶々とするのではなく、「自分の権限の範囲で何ができるか」に集中しましょう。大きな問題は、自分の責任範囲を広げ、上のレベルに上がっていくためのモチベーションに変えることができます。
海外企業との文化の違い
海外での勤務経験がある登壇者からは、日本企業との違いとして「文化」と「データ」に関する見解が示されました。
- 文化: 海外企業、特にジョブディスクリプションが明確な企業では、チェンジマネジメントが必須であり、導入前後で職務内容を書き直すことが行われます。一方、日本の大手企業では、日本的な「間」を重んじ、社員の納得感を醸成しながら進めるスタイルが多いです。
- データ: 海外では、データ入力されていないものは存在しないとみなす文化があり、データに対する考え方や標準化へのこだわりが日本と大きく異なります。リアルタイムなデータで事業の状態を可視化し、それを元に議論する文化が根付いており、これが健全な意思決定につながっています。
登壇者プロフィール

NPO法人
CIO Lounge
友岡賢二
企業のDXを加速するため関西の製造業現役CIOやOBが集まって結成したCIO Loungeメンバー。悩みを抱える企業に寄り添い無償ボランティアでコンサルティングを実践中。本業では製造業のCIO/CDOとして、コミュニティでは「武闘派CIO」として多方面で活躍。
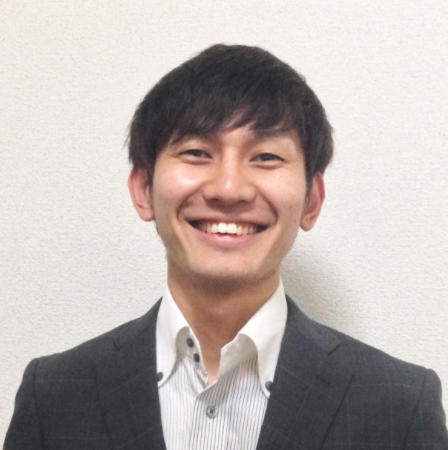
日本マイクロソフト株式会社 クラウド&ソリューション事業本部 サイバーセキュリティ&コンプライアンス統括本部
クラウドエンドポイント技術営業本部 本部長
山本築
セキュリティの技術営業として活動し、2018年より働き方改革推進担当に着任、働き方改革をセキュリティの側面とも合わせながらユーザー企業の業務改革を支援している。

株式会社 AnityA(アニティア) 代表取締役 中野仁
国内・外資ベンダーのエンジニアを経て事業会社の情報システム部門へ転職。メーカー、Webサービス企業でシステム部門の立ち上げやシステム刷新に関わる。2015年から海外を含む基幹システムを刷新する「5並列プロジェクト」を率い、1年半でシステム基盤をシンプルに構築し直すプロジェクトを敢行した。2019年10月からラクスルに移籍。また、2018年にはITコンサル会社AnityAを立ち上げ、代表取締役としてシステム企画、導入についてのコンサルティングを中心に活動している。システムに限らない企業の本質的な変化を実現することが信条。