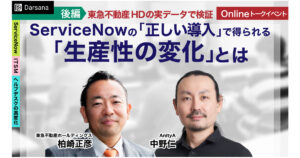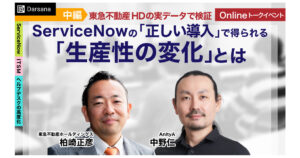2025年6月6日、エンタープライズIT協会主催のクローズドイベントが開催されました。本イベントでは「AIをどう扱うか」をテーマに、サイボウズ、ミクシィ、リクルート、グリー、東急不動産といった各社のAI担当者が登壇し、エンタープライズITにおける生成AI活用の「現在地」、具体的な「成果と課題」、そして「今後の展望」について詳細な議論が交わされました。
本記事では、このセミナーの要点をまとめ、各社のユニークな取り組みとそこから得られる示唆をご紹介します。
各社の生成AI活用事例
サイボウズ:守りと攻めの両輪で進めるAI活用
サイボウズでは、組織的なAI活用を推進するため、「守り(ガバナンス)」「情報共有支援」「攻め(現場での活用)」の三層構造で体制を構築しています。
- 具体的な成果: カスタマーサポート業務にAIを全面的に導入し、問い合わせ1件あたりの対応時間を約25分から約6分へと大幅に短縮。これにより、月間約450時間の工数削減を達成しました。さらに、複数のAI人格(最高のメールを作るAI、ミスのないメールを作るAI)を連携させ、最適な回答を生成する高度な試みも実施しています。
- 課題: 開発者向けAIツールの導入により、年間4,000〜5,000万円ものコストがかかる見込みです。アンケートでは96%が「生産性向上に貢献」と回答する一方、「効果的に活用できているか」という問いへの肯定的な回答は60%に留まり、投資対効果の明確化が課題となっています。
ミクシィ:トップダウンで加速する全社AI投資
ミクシィは経営層の強いリーダーシップのもと、2024年を「AI投資の年」と位置づけ、全社的にAI活用を本格化。ChatGPT Enterpriseを導入するなど積極的な投資を行っています。
- 推進体制: 元CTOの取締役が主導する「AI委員会」を発足し、トップダウンで施策を推進。各部署に「AIアンバサダー」を設置し、現在250件以上の施策が進行中です。
- ツールの利用状況: 2024年3月にChatGPT Enterpriseを本社全社員に導入。MAU(月間アクティブユーザー数)はChatGPTが1,500人超、Geminiが1,200人超と、ChatGPTの利用が優勢です。
- 新技術検証の課題: Googleの「Agent Space」を全社リリースすべく検証中ですが、時間軸の扱いが苦手で無関係な情報が表示される、モデルが古く回答の質が低いといった品質面での課題に直面。実用化にはデータソースの整理が不可欠であることが判明しました。
リクルート:早期導入によるリスク低減とユースケース創出
リクルートは早期からオプトアウト可能なツールを全社展開することで、シャドーITのリスクを低減しつつ、社員が安全にAIを試せる環境を構築。現場主導のコミュニティ運営により、自律的な活用文化を醸成しています。
- 導入ツールと規模: AI Studio(約12,000アカウント)、ChatGPT Enterprise(約2,800)、Gemini(アクティブ約5,500)、Copilot(約2,200)など、ニーズに応じて複数のツールを導入しています。
- 具体的なユースケース: 「リクルートダイレクトスカウト」でのレジュメ自動生成やAIマッチング、「ホットペッパーグルメ」での広告原稿作成効率化、プログラムコードの約1/3をAIが生成するサイトコーディングなど多岐にわたります。
- コミュニティ運営: Teams上に誰でも参加できるコミュニティを設置し、管理者側では想定していなかった活用ニーズの発見や、ユーザー同士での課題解決が活発に行われています。
グリー:予算制約下での創造的な自社開発
グリーは潤沢な予算がない中で、既存のライセンス(Google Workspace)に含まれるGeminiを標準ツールとしつつ、情シスが主体となってAIを活用したユニークな内製ツールを開発しています。
- 基本方針: 追加コストのかからないGeminiの利用を推奨。
- ユニークな取り組み:
- マルチエージェント型バーチャルサービスデスク: 「いかちゃん」「サーモンちゃん」といったキャラクターを持つ複数のAIエージェントを自社開発し、問い合わせ対応の自動化を目指しています。
- ワークフローツールのクローン作成: 予算削減で廃止するワークフローツールの代替を、生成AIと対話しながら開発者が内製。
- Slack絵文字の著作権チェック: ユーザーが登録した絵文字に著作権侵害の恐れがないか、AIで自動チェックする仕組みを導入。
- マルチエージェント型バーチャルサービスデスク: 「いかちゃん」「サーモンちゃん」といったキャラクターを持つ複数のAIエージェントを自社開発し、問い合わせ対応の自動化を目指しています。
東急不動産:非IT企業におけるデータドリブンな現実的アプローチ
東急不動産は、非IT企業における社員のAIへの関心度の低さをデータで可視化。全社一律の施策ではなく、利用データに基づいて活用意欲の高い層にリソースを集中投下する「脱おもてなし」戦略を採っています。
- 社員のAI利用実態: ChatGPTのライセンスを1,263人に配布したものの、実際に利用しているのは半数の648人。さらに、利用の56%は上位100人のヘビーユーザーによるものでした。アンケートでは、社員の55%が「AIは自分の仕事に関係ない」と回答しており、AIへの関心に大きな温度差があることが判明しました。
- 「脱おもてなし」戦略: 利用データに基づき、やる気のない層への教育コストを削減。ITサポートや高度な教育は、AIを積極的に活用している上位20%の社員に集中する方針で、優秀な社員のさらなる生産性向上を目指しています。
- 教育方針の工夫: 高度なプロンプトエンジニアリングは求めず、「隣の席の同僚に話しかけるように、AIと対話してください」と指導。心理的なハードルを下げることで、利用者が倍増する効果が見られました。
最終的な結論と全体討議からの示唆
本セミナーを通じて、各社がAI活用という共通のテーマに多様なアプローチで挑んでいることが明らかになりました。
- 共通の課題:
- ツールの乱立とコスト
- 効果測定の難しさ
- 社員間のリテラシー格差
- 技術進化への追随 これらは、業界や企業規模を問わず共通の課題として浮上しました。
- アプローチの多様性: 潤沢な資金でトップダウンに進めるミクシィ、ガバナンスと現場活用を両立させるサイボウズ、予算の制約を創造性で乗り越えるグリー、そしてデータに基づき割り切った戦略をとる東急不動産など、それぞれの置かれた状況に応じた戦略が展開されています。
- 今後の方向性:
- データドリブンな意思決定の重要性: 感覚や声の大きさではなく、利用データという「ファクト」に基づいて投資判断や教育方針を決めることの有効性が示されました。
- 一点集中からポートフォリオへ: 特定のツールに社運を賭けるのではなく、複数のツールを試しながら、自社に最適な組み合わせ(ポートフォリオ)を見つけていく必要があります。
- 「Gemini」への期待: 最終的な質疑応答で「一つだけ残すなら?」という問いに対し、多くの登壇者がコスト、性能、既存ツールとの連携のバランスから「Gemini」を挙げました。これは今後のエンタープライズAI市場の動向を占う上で注目すべき点です。
総じて、生成AIの企業活用はまだ黎明期であり、各社が試行錯誤を続けています。成功の鍵は、ツールそのものの性能だけでなく、自社の文化や課題に合わせて、いかに現実的かつ戦略的に導入・定着させていくかにあると言えるでしょう。
本イベントにご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。エンタープライズIT協会は、引き続きこのような情報交換の場を提供し、業界全体の発展に貢献してまいります。