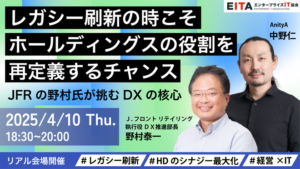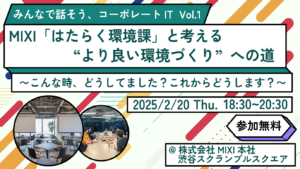2025年6月6日、エンタープライズIT協会が主催する特別セミナーが開催され、国内の主要企業5社(サイボウズ、ミクシィ、リクルート、グリー、東急不動産)のAI担当者が登壇しました。本イベントでは「AIをどう扱うか」をテーマに、各社が現在取り組んでいる生成AIの活用状況、直面している課題、得られた成果、そして今後の展望について活発な議論が交わされました。
本記事では、そのセミナーの概要と、各社の発表から見えてきた共通のテーマや多様なアプローチについて、主要なポイントを抜粋してご紹介します。
目次
企業における生成AI活用の多様なアプローチ
セミナーでは、参加企業がそれぞれの組織文化や事業特性に応じた生成AI活用戦略を展開していることが明らかになりました。
- 「守り」と「攻め」のバランス: ある企業では、AI活用におけるガバナンス体制を強固にしつつ、現場主導の自由な試行を促すことで、組織的なAI活用を推進しています。特定の業務領域では、AI導入により業務効率が大幅に向上した事例も紹介されました。
- 経営層主導の推進: 別の企業では、経営層の強いリーダーシップのもと、全社的なAI投資を加速させています。全社員へのAIツールの積極的な導入を進める一方で、最新技術の検証段階で品質面での課題に直面している現状も共有されました。
- 早期導入とコミュニティ醸成: ある企業は、社員が安全にAIを試せる環境を早期に提供することで、シャドーITのリスクを低減しています。現場主導のコミュニティ運営を通じて、多様なAI活用事例が自律的に生まれる文化を醸成している点が注目されました。
- 予算制約下での創造的内製: 限られたリソースの中で、既存ツールを最大限活用しつつ、情シス部門が主体となってAIを応用したユニークな内製ツールを開発している事例も紹介されました。これは、高額な外部サービスに依存しない、創造的なIT部門のあり方を示唆するものです。
- データに基づく現実的戦略: 非IT企業のある登壇者からは、社員のAIへの関心度合いをデータで可視化し、その上で、活用意欲の高い層にリソースを集中投下するという、非常に戦略的かつ現実的なアプローチが共有されました。心理的なハードルを下げる工夫により、AIツールの利用者が増加したという興味深い話もありました。
全体討議から見えた共通の課題と今後の展望
セミナーの全体討議では、業界や企業規模を問わず、生成AIの導入・運用に共通するいくつかの課題が浮き彫りになりました。
- 共通の課題:
- 複数のAIツールの乱立とそのコスト管理
- AI活用の効果測定の難しさ
- 社員間のAIリテラシー格差
- 急速に進化するAI技術への追随
- 意思決定の重要性: 感覚や声の大きさではなく、実際の利用データという「ファクト」に基づいて投資判断や教育方針を決めることの有効性が強調されました。また、特定のツールに限定せず、複数のツールを試しながら自社に最適な組み合わせ(ポートフォリオ)を見つけていくことの重要性も議論されました。
- 注目のAIツール: 質疑応答の中では、コスト、性能、既存ツールとの連携のバランスから、ある特定のAIツール(本記事では具体名は割愛)が今後のエンタープライズAI市場の動向を占う上で注目すべき存在として挙げられました。
総じて、生成AIの企業活用はまだ試行錯誤の段階にあり、各社が自社の状況に合わせて現実的かつ戦略的なアアプローチを模索しています。ツールの性能だけでなく、組織文化や具体的な課題にいかにフィットさせるかが、成功の鍵となるでしょう。
エンタープライズIT協会は、今後もこのような最新技術に関する情報交換の場を提供し、企業の皆様のデジタル変革を支援してまいります。